執行猶予がつく場合・つかない場合
1 執行猶予とは
執行猶予という言葉は、報道や刑事ドラマでもよく聞く機会があると思います。
執行猶予は、どのような場合に付されるのか、逆に、執行猶予が付されないのはどのような事情がある場合なのかについて、説明します。
⑴ 執行猶予とは何か
ア 執行猶予の意義
刑事事件を起こし、起訴され、裁判で有罪と判断された場合、裁判官から、「被告人を懲役○年に処す」と、判決を言い渡されます。このとき、裁判官が、続けて、「この裁判確定の日から○年の間、その刑の全部の執行を猶予する」などと述べることがあります。これが執行猶予です。有罪判決に基づく刑罰の執行を一定期間猶予する制度であり、刑法25条以下に定められています。
イ 執行猶予の効果
執行猶予を付された場合、本来、懲役刑に処されれば、刑罰の執行を受けるために刑務所に行かなくてはならないところ、その執行が一定期間猶予され、刑務所に行かなくてもよくなります。そして、何事もなく猶予期間を経過すれば、判決の言い渡しの効力がなくなり(刑法27条)、期間が終了した後に刑が執行され刑務所に行く必要もなくなるのです。しかし、罪を犯した事実が消えるわけではありませんので、執行猶予期間中に再度犯罪に手を染めれば、執行猶予は取り消され、前の罪と、新たな罪と、両方で刑罰を受けることになります。
2 どのような場合に執行猶予が付される?
⑴ 執行猶予の制度趣旨
なぜこのような制度が認められるのでしょうか。 懲役・禁固という刑罰を科し、服役することになった場合、生活が大きく変わってしまいます。職を失い、離婚などにより家族を失うこともあります。そうなると、服役を終えても、社会復帰ができずに、再度犯罪に手を染めてしまう可能性もあります。このような刑罰を科すことによる弊害に配慮し、犯罪自体が比較的軽微であり、被告人が十分反省しているような場合には、社会生活を送る中で更生していく方が、むしろ、再犯防止に資すると考えられます。そこで、執行猶予という制度が認められました。
⑵ 刑法25条の定め
上記のような制度趣旨を前提に、刑法25条は、執行猶予を付すことができる場合を以下のように定めています。
【刑法25条1項】
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
これを整理すると、執行猶予を付する条件は以下のようになります。
- 科される刑が、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金である
- 前に禁固以上の刑(禁固、懲役)に処されたことがない
- 前に禁固以上の刑(禁固、懲役)に処されたことがあるが、執行を終えた、執行を免除された日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない(※ ここでいう、刑に処せられたとは、執行猶予を付された場合も含みます。その場合、5年の起算点は、猶予期間終了時です。)
- 執行を猶予すべき情状が認められる
3 執行猶予がつかない場合
執行猶予を付されるには、上の1~3の条件は、クリアしていなくてはなりません。これに引っかかってしまうと、法律上執行猶予を付することができません。そのうえで、執行を猶予すべき情状があるといえれば、執行猶予が付されることになります。以下、執行猶予を法律上付することができないケースを、具体的に見ていきましょう。
※ 4執行を猶予すべき情状に関しては「執行猶予を得るにはどうしたらよいか」の記事をご参照ください。
⑴ 重大事件
1の条件との関係で、まず、科される刑が、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金でないとなりませんので、殺人や強盗などの重大事件の場合は、法定刑の関係から、これに引っかかってしまいます(殺人罪は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役、強盗は5年以上の有期懲役と刑が定められています)。
制度趣旨からしても、重い犯罪の場合は、処罰の必要の方が、これによる弊害への配慮よりも優先されるといえるためです。このようなケースでは、更生のためにも、実刑適用はやむを得ないと考えられます。
殺人、強盗、強制性交などのケースでは、執行猶予はつかないものと考えてよいですが、可能性は0ではありません。自首による軽減や、情状を考慮しての軽減によって、3年以下の判決が言い渡される可能性もあります。その場合には、①の条件はクリアできることになります。
⑵ 前科がある
前科の有無は、まず、2、3の条件との関係で問題となります。2、3の条件より、今回刑を言い渡される罪を犯すより前に、懲役・禁固刑で服役したり、執行猶予付判決を受けたりしていて、服役終了や執行期間満了から、5年が経過していない場合には、執行猶予を付すことができないということになります。そのため、服役終了または執行猶予期間満了から間もなく、再度犯罪行為をしてしまった場合には、執行猶予は付されません。そのように、犯罪を繰り返してしまう場合、社会内での更生が妥当であるとはいいがたいと考えられるため、このような条件が定められています。
懲役・禁固刑を受けた場合に限られるので、以前に罰金刑を受けたことがあるだけなら、この条件との関係では問題はありません。なお、終了から5年を経過していれば、上記条件にはかかりませんが、5年を経過していれば執行猶予がつくというわけではない点には注意が必要です。
前科がある場合は、執行猶予付与については、慎重な判断がされます。例えば、覚醒剤を所持し、懲役1年6月、執行猶予3年という判決を受けた場合、執行猶予期間が終了してから7年ほど経つと、再度覚醒剤所持で裁判となった場合にも、執行猶予が付される傾向にあるようですが、それ以下の期間の間に再犯をしてしまうと、執行猶予が付されるには、特別な事情が必要になってきます。もちろん、犯罪の種類や個別の事情により様々ですが、このように、懲役・禁固刑の前科があると、再び執行猶予が付されるには、かなりの長期間の経過を要することになります。
⑶ 複数件起訴、余罪多数
上にあげた、1~3の条件にかからなくても、複数の犯罪で起訴されていたり、起訴された犯罪は1件でも、余罪が多数あると裁判の中で認定されていた場合、執行猶予が付されにくくなります。
⑷ 反省が認められない
執行猶予を付す趣旨は、社会内での更生を期するところにありますので、明らかに反省の態度が認められないような、社会内で更生できないと判断されるケースでは、執行猶予は付されません。罪を認めていない場合や、反省を示す事情がないような場合は、執行猶予が付される可能性は低くなります。反省を示す事情についても、ただ反省していますと述べるだけでは不十分です。被害者のいる犯罪では、示談をしたり、依存症の場合には専門機関での治療をしたり、客観的な事情として示すことが重要です。
4 執行猶予を目指すために弁護士に相談を
⑴ 執行猶予獲得には適切な主張が必要
執行猶予が付されうるケースなのかどうかは、刑事事件に対応していく方針を決定するにあたって、非常に重要な要素となります。執行猶予となりうる余地があるのであれば、積極的に反省を示す活動をしていくべきです。このような判断には、経験豊富な弁護士のアドバイスが必要になります。また、社会内で更生すべきと認められるだけの事情を準備し、裁判で主張していくためにも、弁護士による適切な対応が必要になるでしょう。
⑵ 不起訴処分となることも
そのような活動に早期に着手した結果、起訴されず、前科がつくこと自体を避けられることもあります。例えば、示談ができていれば、検察官はこれを重視して、不起訴処分とするということも多々見られます。
⑶ まずはご相談ください
執行猶予獲得や、これを目指していくかの判断には、弁護士のアドバイスや対応が必要になります。早期にご相談いただくことで、できることも増えますし、起訴されること自体を回避できる可能性もあります。刑事事件を起こしてしまったという方は、オリオン法律事務所までご相談ください。
著作者:弁護士 枝窪 史郎
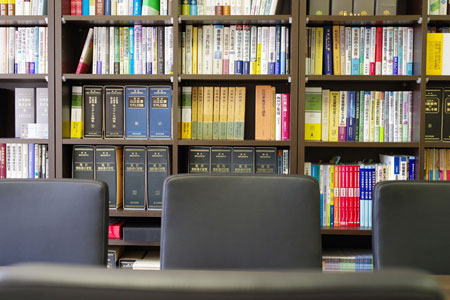

バナースペース
※スマホでご覧の方へ
※本サイト内の各ページへはページ左上のボタンからリンクして下さい。
弁護士法人オリオン法律事務所
・オリオン渋谷事務所
東京都渋谷区神南1-11-4
FPGlinks神南6階
TEL 03-5489-7025
・オリオン池袋事務所
東京都豊島区南池袋2-15-3
前田ビル3階
TEL 03-5957-3650
・オリオン横浜事務所
横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル2階
TEL 045-900-2817
・オリオン川崎事務所
川崎市川崎区砂子1-7-1
DK川崎ビル7階
TEL 044-222-3288
営業時間
平日… 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:00
対応地域
・東京都
豊島区│板橋区│練馬区│文京区│新宿区│中野区│北区│台東区│墨田区│荒川区│足立区│葛飾区│江東区│港区│渋谷区│目黒区│世田谷区│品川区│杉並区│大田区│西東京市│東久留米市│清瀬市│武蔵野市│三鷹市│小金井市│その他の市区町村
・埼玉県
さいたま市│川口市│戸田市│蕨市│和光市│朝霞市│新座市│志木市│その他の市町村
・神奈川県
横浜市│川崎市│大和市│厚木市│相模原市│鎌倉市│綾瀬市│座間市│海老名市│藤沢市│逗子市│横須賀市│茅ヶ崎市│平塚市│その他の市町村