再度の執行猶予とその条件
1 執行猶予について
⑴ 執行猶予とは
刑事事件を起こし、起訴され、裁判で有罪と判断された場合、裁判官から、「被告人を懲役○年に処す」と、判決主文を述べるのに続けて、「この裁判確定の日から○年の間、その刑の全部の執行を猶予する」などと述べることがあります。 これを執行猶予といい、有罪判決に基づく刑の執行を、一定期間猶予する制度として、法律に定められています。執行猶予という言葉自体は、耳にしたことがある方も多いと思います。ただ、その効果や定めについて、正しく理解していないと、せっかく付された執行猶予を取り消されてしまうことになりかねません。
⑵ 執行猶予の効果
本来、懲役刑に処されれば、刑罰の執行を受けるために刑務所に行かなくてはならないところ、執行猶予を付された場合、その執行が一定期間猶予され、刑務所に行かなくてもよくなります。そして、何事もなく猶予期間を経過すれば、判決の言い渡しの効力がなくなり(刑法27条)、期間が終了した後に刑が執行され刑務所に行く必要もなくなるのです。
つまり、執行猶予が付されれば、懲役刑を科されたにもかかわらず、普段通りの生活ができ、家族とも暮らせるし、会社や学校にも行けることになるのです。しかし、注意しなくてはならないのは、執行猶予が付されても、罪を犯した事実が消えるわけではないということです。
2 執行猶予中に罪を犯すとどうなる?
何事もなく猶予期間を終えれば、と述べましたが、この何事もないという言葉の意味は、基本的には、執行猶予期間中に再び罪を犯さないということです。執行猶予期間中に罪を犯すと、どうなるのでしょうか。
⑴ 執行猶予の取り消し
ア 執行猶予が取り消される
刑法26条以下では、一定の場合に、執行猶予が取り消されることを定めています。
刑法26条第1号より、「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」には、必要的に執行猶予が取り消され、刑法26条の2第1号より、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」は、裁量により執行猶予を取り消されうることになります。
イ 具体的な帰結
執行猶予が取り消されると、具体的にはどうなるのでしょうか。
この場合、①執行猶予に係る罪と、②新たに犯した罪と2罪が存在するわけですが、①の罪に関する執行猶予が取り消される結果、①の刑の執行を受けなければなりません。また、②の罪に関しても、執行猶予を付されていないので、通常通り、刑を執行されます。結果、両罪を合わせた期間の懲役に服さなくてはならないということになります。
ウ 注意しなければならないこと
一般に、これを理解していれば、執行猶予期間中に、再度罪を犯すことはないと考えられそうですが、以下のような場合に注意が必要です。
⒜ 交通違反
交通違反も、内容等によって、刑事罰の対象になるものがあります。故意でなくとも刑事罰の対象になりうることから、自分の意志だけで制御できるものではなく、執行猶予中は、運転にも注意が必要です。運転をしないという選択もありうるでしょう。
⒝ 依存症が疑われるケース
薬物事犯のような典型的な依存症のみならず、摂食障害に密接に関連する窃盗や、痴漢・盗撮といった性犯罪は、依存傾向が認められます。これも、ある意味で、自分の意思で制御することができないものといえ、執行猶予を付された際には、裁判の中で、二度としないと固く誓っていたにもかかわらず、猶予期間中に再度犯罪に手を染めてしまう方が多いです。
⑵ 再度の執行猶予
執行猶予期間中に罪を犯してしまった場合、必ず執行猶予が取り消されるのかというと、そうではりません。 俗にダブル執行猶予といわれる、一定の条件を満たせば、新しい罪について再度の執行猶予が付され、前の執行猶予が取り消されない仕組みがあります。
ア 再度の執行猶予付与の条件
刑法25条3項が、再度の執行猶予について定めています。同条項の定めを整理すると、再度の執行猶予が付される条件は、以下になります。
- 執行猶予期間中に罪を犯したこと
- 新たに犯した罪に対する判決が1年以下の懲役または禁錮であること
- 情状に特に酌量すべきものがあること
- 前に執行猶予を付された際に保護観察に付されていないこと
イ 獲得は非常に難しい
このように、再度の執行猶予が付される余地はありますが、実際にこれを獲得するのは困難が伴います。
まず、2との関係でいえば、新たな罪の判決が、懲役1年以下でなくてはなりません。依存傾向が強く、執行猶予期間中の再犯になりやすいといえる薬物事犯を例に挙げると、そもそも初犯であっても、(行為態様にもよりますが)1年以下の懲役判決がされないことも多く、再犯時には、前刑よりも加算された刑が科されるため、1年を下回るケースは少ないといえます。万引きなどのケースで、2の条件を満たす傾向が認められます。
3に関して、1回目の執行猶予が付される際も情状について判断がありましたが、再度の執行猶予では、「特に」「酌量すべき」と認められる必要があります。情状とは、犯罪の行為態様、結果の程度、これに至る経緯といった犯情や、年齢・性別等の属性、示談の有無、反省、更生可能性(意欲や環境)、監督の有無、再犯可能性、前科前歴といった一般情状をいいますが、これについて、厳しく判断されることになります。
以上の結果、再度の執行猶予を付される割合は、執行猶予中の再犯者の5%ほどしかないと言われています。
3 執行猶予期満了直前に罪を犯したらどうなる?
ここまで説明してきたのは、執行猶予期間中に再度罪を犯してしまったケースですが、執行猶予期間満了の直前に罪を犯した場合には多少異なるところがあります。
刑法26条や、27条の定めから、執行猶予期間が満了していれば、前の刑に関しては、執行猶予が取り消されることはなく、懲役に服する必要はありません。では、罪を犯したとは何を指すのでしょうか。罪を犯したという点について、正確には、刑法26条第1号が、「刑に処せられ」た場合としています。刑に処せられるとは、有罪の確定判決を受けることをいいますので、有罪の判決が確定したときが、再び罪を犯したときとなります。
以上より、再度の犯罪行為自体は、執行猶予期間満了前にしてしまったとしても、刑事手続に時間がかかることで,再度の判決の確定が前の刑の執行猶予期間満了後であれば、前の刑の執行猶予は取り消されないことになります。
新たに犯した罪について執行猶予が付される可能性は非常に低いことから、刑に服することにはなると考えられますが、前の罪の刑については服さなくてもよいことになります。
4 再度の執行猶予の可能性は弁護士に相談を
⑴ 再度の執行猶予獲得には適切な主張が必要
このように、再度の執行猶予獲得には困難が伴いますが、これを付されるべき事情を満たしている場合は、適切な主張により、再度の執行猶予獲得を目指す価値があります。そのためには、刑事事件の経験豊富な弁護士による適切な対応が必要になるでしょう。
⑵ まずはご相談ください
再度の執行猶予獲得に必要な情状を主張していくためには、事件の早期段階から、準備を行っていく必要があります。
例えば、依存症が疑われるケースであれば、専門の治療機関に、適切な診断をしてもらい、時間を掛けて、これと真摯に向き合いながら治療していくことなどが求められます。早期に経験豊富な弁護士に相談する必要があるといえます。
刑事事件を起こしてしまったという方は、オリオン法律事務所までご相談ください。
著作者:弁護士 枝窪 史郎
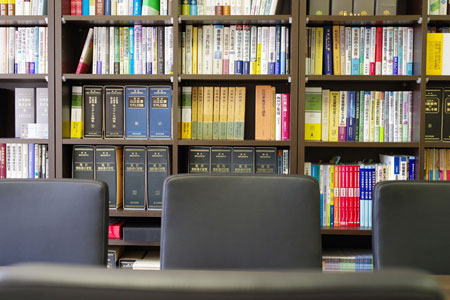

バナースペース
※スマホでご覧の方へ
※本サイト内の各ページへはページ左上のボタンからリンクして下さい。
弁護士法人オリオン法律事務所
・オリオン渋谷事務所
東京都渋谷区神南1-11-4
FPGlinks神南6階
TEL 03-5489-7025
・オリオン池袋事務所
東京都豊島区南池袋2-15-3
前田ビル3階
TEL 03-5957-3650
・オリオン横浜事務所
横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル2階
TEL 045-900-2817
・オリオン川崎事務所
川崎市川崎区砂子1-7-1
DK川崎ビル7階
TEL 044-222-3288
営業時間
平日… 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:00
対応地域
・東京都
豊島区│板橋区│練馬区│文京区│新宿区│中野区│北区│台東区│墨田区│荒川区│足立区│葛飾区│江東区│港区│渋谷区│目黒区│世田谷区│品川区│杉並区│大田区│西東京市│東久留米市│清瀬市│武蔵野市│三鷹市│小金井市│その他の市区町村
・埼玉県
さいたま市│川口市│戸田市│蕨市│和光市│朝霞市│新座市│志木市│その他の市町村
・神奈川県
横浜市│川崎市│大和市│厚木市│相模原市│鎌倉市│綾瀬市│座間市│海老名市│藤沢市│逗子市│横須賀市│茅ヶ崎市│平塚市│その他の市町村