刑事裁判はどう進み何をすればよいか?
1 刑事裁判とは
何らかの罪に該当する行為をしてしまった場合、裁判を行うというイメージをお持ちの方が多いと思います。
では、裁判では何を目的として、具体的にはどういった手続が行われるのでしょうか。
⑴ 刑事事件の流れ
会社帰りに渋谷の居酒屋で酔って人を殴ってしまった、渋谷駅で盗撮をしてしまった、このように、犯罪に該当する行為をしてしまった場合、以下のような流れで事件は進んでいきます。
まずは、被害届や通報、職務質問などにより、犯罪に該当し得る事実が発覚し、警察が、事件性があると判断した場合は、刑事事件として立件され、捜査がされます。この際、逮捕という身柄拘束が伴うこともあります。
警察が一定の捜査を終えると、その事件を、検察に送致します。 送致を受けた検察官は、引き続き事件を捜査し、起訴をするかどうかを決めます。この間の捜査が、勾留という身柄拘束手続のうえで行われることもあります。検察官が起訴をすると、原則的には、裁判が行われることになります。
⑵ 裁判とは何をする手続きか
刑事事件の裁判とは、被告人が、罪を犯したのか否か、その罪の重さについて、裁判所が判断する手続です。
検察官は、罪を犯した疑いがある人物について、裁判にかけることを請求(起訴)し、裁判の場で、当該人物が罪を犯したことを、各種の証拠と共に主張します。起訴された人物は、被告人と呼ばれます。被告人の側では、罪を犯していないことや、罪を犯したとしても酌むべき事情があるので執行猶予を付されるべきであるとか、量刑を軽くするべきであるといったことを主張します。そして、裁判所が、法廷に顕出された事実や証拠を基に、罪を犯したのか否か、その罪の重さを判断します。
被告人の側でも主張をすると述べましたが、一方当事者である検察官が法のエキスパートであるのに対し、被告人には、法的な知識は多くないのが通常です。そのため、被告人の側には、専門家である弁護士がつき、手続を進めていきます。
⑶ 起訴されても正式裁判をしない場合も?
起訴をされた場合、必ず裁判をやるのかというと、そういうわけではありません。被疑者が罪を認めていて、課される刑が100万円以下の罰金・科料である場合、検察官は、被疑者の同意の下、略式起訴という書面審理だけで終わる簡易な裁判手続を請求することができます。このような略式裁判を経て、略式命令で罰金等が科される場合、実際に法廷で裁判を行うことはありません。イメージとして、軽微な事件であり、初犯だったりする場合には、略式手続となることが多いです。また、捜査をした結果、そもそも起訴をしないということもあります。
2 刑事裁判の具体的手続
⑴ 手続の流れ
刑事裁判は、以下の流れで手続きが進んでいきます。
罪を犯していないと争う否認事件や、複雑な事件の場合は、以下の手続が複数回の期日に分けられて行われますが、罪を認めているような事件であれば、1回の裁判期日で審理を終えます。
【手続の流れ】
① 冒頭手続
Ⅰ 人定質問 Ⅱ 起訴状朗読 Ⅲ 黙秘権等の権利告知 Ⅳ 被告人及び弁護人の意見陳述
② 証拠調べ手続
Ⅰ 冒頭陳述 Ⅱ 検察官による証拠調べ請求→弁護人の証拠意見→検察官の証拠説明 Ⅲ 弁護人による証拠調べ請求→検察官の証拠意見→弁護人の証拠説明 Ⅳ 証人尋問 Ⅴ 被告人質問
③ 当事者による最終意見陳述
Ⅰ 検察官の論告・求刑 Ⅱ 弁護人の最終弁論 Ⅲ 被告人の最終陳述
④ 判決言い渡し
【各手続きの詳細】
① 冒頭手続
- Ⅰ 人定質問
- 被告人の氏名、生年月日、本籍、住所、職業の確認です。 被告人が、裁判官の質問に自ら答える形で行われます。
- Ⅱ 起訴状朗読
- 検察官が起訴状に記載された公訴事実と罪名及び罰条を読み上げます。なお、起訴状は起訴の段階で予め被告人には交付されています。
- Ⅲ 黙秘権等の権利告知
- 裁判官から被告人に、法廷で聞かれたことについて、黙秘する権利(黙秘権)があることが告げられます。その際、法廷で話したことは証拠となり、被告人にとって有利にも不利にもなることも説明されます。
- Ⅳ 被告人及び弁護人の意見陳述
- 裁判官から、検察官が読み上げた起訴状の内容に間違いはないか聞かれます。 被告人は、起訴状に誤りがなければその旨を、誤りがあれば、何が間違っているのかを、証言台の前で答えます(罪状認否)。
被告人の罪状認否の後、弁護人も意見を述べますが、基本的には、被告人と同意見である旨を述べます。
② 証拠調べ手続
- Ⅰ 検察官の冒頭陳述
- 検察官が、証拠により証明しようとしている、事件の内容等について説明する手続です。これに続き、公判前整理手続を行った裁判員裁判事件や、複雑な事件などでは、弁護士が同様に冒頭陳述を行います。
- Ⅱ 検察官による証拠調べ請求→弁護人の証拠意見→検察官の証拠説明
-
ア まず、検察官から、裁判に提出したい証拠について、証拠調べ請求をします。 証拠には、凶器や薬物などの物、捜査段階での被告人や証人の供述を記載した書面、証人などがあります。 なお、請求予定である証拠については、裁判に先立って被告人側に開示されています。
イ 次に、弁護士が、検察官が請求する証拠について、提出することに同意するか否かの意見を述べます。この意見には、全部同意する場合や、一部同意し、一部不同意とする場合などがあります。 裁判官は、同意見を踏まえ、証拠として採用するか否かを決定します。
ウ 採用された証拠については、検察官が、証拠の内容について、概要を説明します。
- Ⅲ 弁護人による証拠調べ請求→検察官の証拠意見→弁護人の証拠説明
-
ア 弁護人も、裁判に提出したい証拠を請求します。
否認事件であれば、検察官の主張する事実や証拠を否定するに足る様々な証拠を提出することが考えられます。
罪を認めている場合であれば、情状に関する証拠として、今後被告人を監督する人物や、被告人の事件前後の生活状況を知る人などに証人尋問することを請求して、刑の軽減などを目指していくことが多いです。イ こちらも、検察官の意見を踏まえ、裁判官が証拠の採否を決定します。なお、弁護人が請求する予定の証拠も、事前に検察官には開示します。
ウ 採用された証拠については、弁護人が証拠の概要を説明します。
- Ⅳ 証人尋問
- 書面や物などの証拠で採用されたものは、基本的に、概要の説明で調べは終了し、法廷の場でそれ以上調べたりすることはありません。これに対し、証人については、法廷の場で、当事者双方が質問をし、答えてもらった内容が、証拠となることになります。
まず、請求した側が質問をし、続いて、反対当事者の側が質問をします。その後、必要に応じて、再度双方が質問をする場合があり、その後、裁判官が質問をします。 - Ⅴ 被告人質問
- 被告人に対し、事件の内容に関すること、被害者に対してどう思っているか、今後どうしていくのかなどをまず弁護人が質問し、答えてもらいます。続いて検察官の質問があり、必要に応じて、弁護人から再度質問をした後、裁判官からの質問となります。 ここで答えた内容は、証拠として扱われます。
③ 当事者による最終意見陳述
- Ⅰ 検察官による論告・求刑
- 検察官が、法廷に顕出された証拠に基づいて、事実や法律の適用についての意見を述べ、最後に、被告人にどれほどの刑罰を求めるかを述べます。
- Ⅱ 弁護士による最終弁論
- 弁護士が、法廷に顕出された証拠に基づいて、被告人が無罪であること(否認事件の場合)や、被告人に執行猶予を付すべきこと、刑を軽減すべきことを、理由と共に説得的に主張します。
- Ⅲ 被告人の最終陳述
- 最後に、被告人が事件について何か言いたいことがあれば述べることができます。
⑵ 被告人がすることと注意点
以上の手続を踏まえると、裁判の場で、被告人となった人が実際に何かを述べたりするのは、以下の手続の場面となります。それぞれの場面で注意すべき点を説明します。
ア 人定質問
氏名、生年月日、住所は問題ないと思いますが、本籍は述べられるように事前に確認しておきましょう。職業については、会社員や、アルバイト、学生など、自分の認識する一般的な属性を述べれば問題ありません。訂正等すべきであれば、裁判官から確認されます。
イ 罪状認否
起訴状に記載された事実について、確認される場面です。予め、起訴状を読み、どう答えるべきか、弁護士と相談しましょう。
ウ 被告人質問
刑事裁判の場で、被告人が最も多くのことを語る場面が被告人質問です。基本的には、一問一答形式で進んでいきます。否認事件であれば、事件の内容について、どのような行動をしたのか、詳細を語っていくことになるでしょう。罪を認めている場合でも、事件の内容について、あらためて、被告人の口から話を聞くことは重要です。捜査段階で作成された調書が、被告人の認識を正確に示すものとは限りません。
とはいえ、罪を認めている場合は、反省や、今後二度と罪を犯さないことを示すことも非常に重要になります。何が原因で罪を犯したのか、具体的な再犯防止策、その取り組みの詳細、被害者に対する思いなどを話していくことになります。
弁護士からの質問については、事前に話し合いをして、どのようなことを聞いていくかを知ったうえで臨むことができます。これに対し、検察官、裁判官の質問は、事前に内容を知ることはできません。しかし、経験のある弁護士であれば、どのようなことを聞かれるかについて、一定の予測をすることが可能です。そのため、予め聞かれるであろうことについて、しっかり考えておくことで、慌てずに対応することができます。
ただ、注意すべきなのは、被告人質問は、予め質問と答えを準備し、暗記したことを述べる場ではないということです。 当然、上記のように一定の準備は必要ですが、事件について、弁護士と話し合って、自分自身で、どう認識し、どう考え、今後どうしていくかを考えることです。
エ 最終意見陳述
裁判から、審理の最後に、何か言いたいことがあるか、陳述を促されます。
罪を認めている場合は、被害者の方への気持ちや、事件に対する反省、今後への取り組みなどについて、簡潔に話すことができるとよいと思われます。何もなければ特にないとして構いませんし、発言内容自体は自由ではありますが、罪を軽くしてくださいというような発言は逆効果であると思われます。
3 弁護士に相談を
⑴ 取り調べ対応のアドバイス
刑事裁判での手続きについて説明してきましたが、刑事裁判では、それまでの捜査で取り調べた内容が前提となってきます。例えば、取り調べで言ったことと全く違う話を裁判でした場合、裁判で話した内容が真実なのだとしても、そのように理解してもらうのは困難が伴います。適切に裁判手続を進め、不利な判決とならないようにするには、取り調べ対応から、弁護士に相談し、アドバイスを受けておく必要があります。
⑵ 裁判にならないですむことも
事件の初期から弁護士がつき、例えば被害者の方と示談をするなどの活動により、そもそも裁判になること自体を回避することもできます。
⑶ 公判対応
刑事裁判の手続は、そもそも弁護士でなければ到底対応できないような手続が多々あります。経験豊富な弁護士が、対応することにより、充実した公判対応及び事前準備により、よい結果を得られる可能性が高くなります。
⑷ まずはご相談ください
刑事裁判でよい結果を得るためには、このように、事件の初期段階から、経験豊富な弁護士に相談することが必要です。刑事事件を起こしてしまったという方は、オリオン法律事務所渋谷支部までご相談ください。渋谷エリアを含む広い地域での刑事事件対応経験を有する弁護士がお話をお伺いいたします。
著作者:弁護士 枝窪 史郎
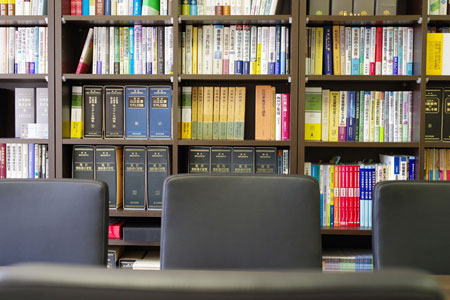

バナースペース
※スマホでご覧の方へ
※本サイト内の各ページへはページ左上のボタンからリンクして下さい。
弁護士法人オリオン法律事務所
・オリオン渋谷事務所
東京都渋谷区神南1-11-4
FPGlinks神南6階
TEL 03-5489-7025
・オリオン池袋事務所
東京都豊島区南池袋2-15-3
前田ビル3階
TEL 03-5957-3650
・オリオン横浜事務所
横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル2階
TEL 045-900-2817
・オリオン川崎事務所
川崎市川崎区砂子1-7-1
DK川崎ビル7階
TEL 044-222-3288
営業時間
平日… 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:00
対応地域
・東京都
豊島区│板橋区│練馬区│文京区│新宿区│中野区│北区│台東区│墨田区│荒川区│足立区│葛飾区│江東区│港区│渋谷区│目黒区│世田谷区│品川区│杉並区│大田区│西東京市│東久留米市│清瀬市│武蔵野市│三鷹市│小金井市│その他の市区町村
・埼玉県
さいたま市│川口市│戸田市│蕨市│和光市│朝霞市│新座市│志木市│その他の市町村
・神奈川県
横浜市│川崎市│大和市│厚木市│相模原市│鎌倉市│綾瀬市│座間市│海老名市│藤沢市│逗子市│横須賀市│茅ヶ崎市│平塚市│その他の市町村